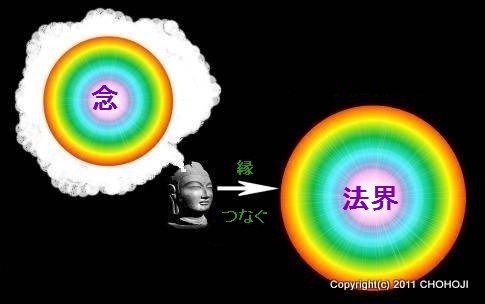
繋縁法界 縁を法界につなぐ
円頓章 解説
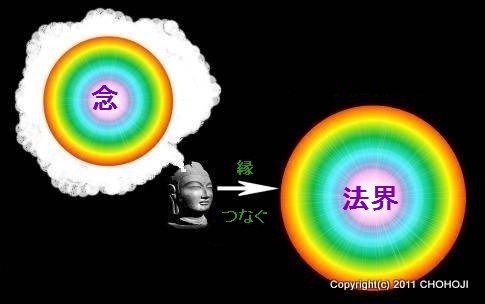
繋縁法界 縁を法界につなぐ
これは、天台宗で最もよく使うお経です
学問的な解説がお好きな方は、それなりの学者先生のお書きになった本をお読みください
ここでは仏教的な考え方のスタイルを知って頂くための解説をしてみようと思います

圓(えん)とは
まどか、です
丸
円満、円熟、など、完全であること、欠けていないことを言いたいわけです
完全無欠であること、です
頓(とん)とは
速やかに、素早く、という意味で
圓頓、で
完全無欠に、素早く、ということになります
で、この圓頓章は、「完全無欠に、素早く、真実に目覚める教え」、といった意味になります
手早く言うと、苦行するとか、修行するとか、刻苦精励ガンバルとか、学問を修める、とか、関係ないです
いつから、仏教が、「坐禅瞑想して、精進努力を重ね、悟りを開く」、ことになったか知りませんが、ここにはそんなことは書いてありません
目覚めるのには時間は必要ありません
目覚めるのには努力も、経験も、関係ありません
皆さん、夜寝て朝になると目が覚めますが、どんな努力をなさってますか?
なんにも思い当たらないんじゃないですか
仏教の、仏(ぶつ)という言葉は、サンスクリット語のbodhi(ボーディ)の音訳です
bodhiとは、目が覚める、という意味に使われていました
そこんとこがですね、一神教の、「なになにの神を信じ」、とか、「神に仕える」とか、と、まるきり違うロジックなのですよ
で、仏の教で、教えはありますが、これは、ギリシャ哲学の古典に学ぶ、とかと同じノリで、含蓄があるから面白い、で片づくわけです
ですので、西洋社会からは、仏教は哲学の一種と見なされる時も多いです
ま、なんでもいいです
本当の事を言ってるだけですから

頓は、時間の経過が必要無い、ということなんですが
むろん、仏教には時間の経過が必要な手段もあります
それを漸教(ぜんきょう)と言います
漸次、とか、徐々に、逐次、しだいに、といったニュアンスです
天台では、お釈迦様の説教を、頓教と漸教に分けて考えています
頓・・・時間が必要ない、あっという間、すぐ
漸・・・時間が必要、修行も必要、手間暇かかる
考えるまでもなく、漸教は、必要ありません
で、方便(ほうべん)と言って、正しい、というか、簡単な方法に導くための仮の手段としています
嘘も方便、と言いますね
このことについては、天台は、もう1200年やっていますから、精緻な分析があるのですが、ザックリ省略します
書いてたら、このサイトの読者がいなくなります(^^;)
圓の方も、中国天台でお釈迦様の説法を蔵通別円に分類して、これに、日本で密教を加えて、蔵、通、別、円、秘密、不定と、カテゴリーを作りました
まあ、知らなくても困りません
圓頓だけ、わかっていたら間に合います
たとえてみると
コンピューターがありますね
OSに、windows2000、XP、VISTAと同じ系列ですね
あるいは、Linuxは、かなりいろいろ種類があります
Macもある
と、いろいろコンピュータを動かす、基本プログラムであるOSがあるわけです
で、そのOSの上で、各種実用ソフトが動きます
で、そのOSもBIOSという、もっと基本になるルールの上で動いています
BIOSはコンピュータという電子機械で、電気信号の羅列であるOSを使えるようにします
仏教は、このBIOSを触ろうとしてるんです
一神教は、Windows、Linux、MacといったOSのうち、どれか一つと契約して帰依するのでしょうね
まあ、二つのOSは同時に使えませんから
それでも、仕事をするのにWindowsだけマスターしてれば全然間に合いますよね
神道の八百万の神々は、数々のユーティリティーソフトということになります
密教とか魔法の、霊的な技術は、レジストリの操作なんですよ
あー、わけわかんなくなるので、このへんでやめときますが、
たとえてみれば、ですよ、仏教のしようとしてる仕事のレベルはそんなもんだ、ということです
BIOSはシンプルでセキュアで堅牢であればあるほど、いい、ということですね
で、圓、頓、です

愛想が無いんで、いちおう天台教学のさわりを説明しときますが、まあ、精緻ですよ
それで、ちゃんと何でも説明できるようになってます
そりゃ、日本に来てからも1200年やってるんですから
で、温故知新です
古きを尋ねて新しきを知る
古典、聖典から自分なりの知恵を学べばいいんじゃないですか
これが、キリスト教でも、イスラムでも、ギリシャ哲学でも、テキストがきちんと整備されてて、その世界の中では辻褄があってます
で、辻褄があってれば、世界の矛盾やら、不条理やらももう少しなんとかなっていそうなもんですが、むしろ、ややこしさが増しているのが現実です
つまり、まだまだ改善の余地があるか、あるいは、やりかたが間違っているかですね
で、大統一理論とか妄想するわけですが、理屈を追っかけてると無限ループになる、と考えてるのが仏教です
観察する対象と、観察者が別々である限り、やっぱり、別々なんで
完全な理解、つまり悟りじゃないと
悟り、とは左側の「りっしんべん」は立心偏と書いて、心のことです
だから、悟り、とは、吾が心、です
漢字の成り立ちで言うとね
探さなくても、ここにあるんだよね・・・
で、観察対象が理で、観察者は智です
理と智が、てんでんばらばらな状態が、「妄想」「狂信」などでしょうなぁ
理に智を近づけようとするのが、科学であり、学問でしょうね
理=智を、不二(ふに)と言います
不二屋じゃないよ、仏教のテクニカルタームです
理と智の合一、統一、統合、合体、一体化、がつまり、仏教が目指している悟りです
観察対象を完全に理解するには、観察対象と合体すればいい、ということですね
世界を理解するには、世界になればいい、悪や不善を理解するには、悪や不善になればいい
とまあ、そういうことになります
坐禅とか、仏教の瞑想は、それをやってるわけよ
世界(観察対象)との一体化を、瞑想状態の時に経験しようとするわけです
これはですね、瞑想状態が普通に生活してるときも継続したら、やってられません
それで、時間を区切ってすることを奨励してます
それを、修行とか、まあ、言ってるんでしょうね
ああ、ですから、慈悲とか愛は、理智不二の状態から言えば、自分がかわいいってことになりますね
ここらへんが、仏教的な慈悲の考えかたですね
誰だって、自分が一番かわいいわけで、正直なんですよ、仏教は
だから、仏教の目的は慈悲じゃなくて、理智不二です
五時八教
五時(お釈迦様の説教を時系列にならべたもの)
華厳時 (華厳経)
鹿苑時 (阿含経)
方等時 (維摩・思益・金光明・勝鬘等の大乗経)
般若時 (諸種の般若経)
法華・涅槃時(法華経・涅槃経)
化儀四教(衆生を導く方法論による分類)
頓教 仏の悟りそのものの教説
漸教 浅略から次第に深く説く教説
秘密教 相互に知られず、能力に応じて理解される教説
不定教 教示をうけた側で、能力に応じて理解される教説
化法四教(教理内容による分類)
三蔵教 小乗仏教
通教 声聞・縁覚・菩薩に共通した教法
別教 一般的な大乗仏教
円教 天台の教法

理智不二は、弘法大師の学説でもあります
弘法大師が、入唐の前、奈良の東大寺の大仏に「願わくば不二を与えたまえ」と祈願し、大日経の存在を教示されたのは有名な話です
これは、能観(のうかん)、所観(しょかん)とも言い
所観が、観察対象である理で、能観が観察主体である智になります
真実であるところの所観と、その観察者である能観を、いかに等しくするか、がつまり、世界の理解であって、言葉による小奇麗な説明など、最初から眼中に無いのです
世界の完璧な説明、ではなくて、世界そのものになる、ことが仏教の目標です
それで、神と人、霊と人、といった、相対的な関係は、仏教は目指していません
一神教的な、神は人に君臨し、人は神に従う、といった関係を、仏教は求めていません
仏教は、さまざまな神々、毘沙門天、大黒天、天女、竜、夜叉、阿修羅、地神、鬼神、等々、と交流したり、助けてもらったり、しますが、ご利益を頂くのが目的ではありません
現今の祈祷寺院で行われている祈祷や法要は、今風の口当たりのいい、受けねらいの部分であって、それは、気休めです
ご利益があるのは、仏教がウソをついてない証明のためであって、馬の口の前のニンジンです
理趣経には、「欲などで世間を整え」と、欲望を満たすことで、仏教に導くことが書かれてます
さて
ざっくり、大雑把に総括すると、理智不二とか能観所観の合一とか、観察対象と観察者が一如になった状態のことを天台学で実相(じっそう)と言います
圓頓者 初縁實相 (えんどんしゃ、しょえんじっそう)
圓頓とは、初めに實相を縁ず
生命の実相、とか、法華経系の新興宗教で言いますが、「實相」というのは、もともとは天台学のテクニカルタームですね
で、さすが、圓頓です
最初に結論を言ってしまってますので、これで終わりです
まあ、それじゃ、あまりに分かりにくいので、この後ろは全部、意味の説明です
完全無欠で素早い方法は、まず最初に「実相」に意識を集中することである
といった意味でしょうか
縁ず、というのが実は、幅広い意味をもっているのですが
まあ、円頓章では無理して短く書いてますので、ここは、こんなもんでしょう
仏教全般、実相を得る方法、と言いますか、理と智を合一させる方法を、止観(しかん)と一括りにします
仏教の方法論は、止観で全て説明がつくようにできてます
止とは、制感です
観とは、観想です
感覚を静めて、イメージを想います
止を強調したり、観を強調したり、様々な方法が編み出されましたが、仏教は止観からははずれません
あー、だから、神に頼む、仏菩薩に願う、というのは、方便であって、急場しのぎです
仏教的には、神になる、仏菩薩になる、ことを目指します

実相ということで言うと
やはり、弘法大師の声字実相義(しょうじじっそうぎ)のことに触れないわけにいきませんが、これは、Terra Free Talk のほうでかなり書いたので、さわりだけにしときます
声(意志ある存在の発する言葉、音、波動、バイブレーションですね)
字(文字ですが、広い意味で、眼耳鼻舌身に感じるられる感覚すべてを、メッセージとして受け止めるということです)
で、声と字は、セットで不可分です
声字は実相だ、と、まあ、そういうことが言いたいわけです
世界は、「意味のある波動」であり、自分に向けられたメッセージだとね
それで、弘法大師の場合、この波動で宇宙全般、世界が成り立っていると、そういう説明をするわけです
このあたりから、量子論のSuper Position に繋がっていくんですが、それはさておき
「声字を発する意志ある存在」、を言わないんですよ
弘法大師は
ここらへんで、理智不二なんですけど
つまり、私は世界だと
吾が心が、世界だと
世界は声字だと
三段論法で、私は声字だと
わかってしまうと、世界、イコール、自分で
世界を作り出しているのは、自分で
私は声字だと

なんで、吾が心が悟りであり、世界であり、宇宙の森羅万象なのか、ということなんですけど
これは、仏教の最も基本的な考え方の、唯識観です
唯識観はつまり、智です
心に感じる、ありのままのことが世界の全てです
眼耳鼻舌身の感覚器官によって感じたことが、世界の姿です
仏教的には、世界は自分の外側にあるのではなくて、自分の心に生じたものです
それで、この自分の心を、自分でどうにも好きなように操れないというのが現実なのですな
もう一つの理のほうは空観になります
縁によって生じ、縁によって滅する縁起の世界です
唯識観は、主に華厳経で説かれます
お釈迦様の悟りそのものを説いた、哲学的世界観とされています
密教で金剛頂経系の経典になります
空観は、般若心経などの般若経典(般若とは、サンスクリットで智慧のこと)で説かれます
密教では、大日経系の経典になります
経典の解説をしてるといつまでたっても先に進みませんので、これも省略しますが、仏教は理・空観と智・唯識観の見当がつけば、ほぼ構造を理解したことになります
で、その唯識観ですが、人それぞれ十人十色、皆考えてることが違います
同じリンゴを見ても、見える角度はそれぞれ全部違います
結論が一緒でも、考え方や理由はそれぞれ皆違います
一つとして同じ心は無い、ということですね
まあ、わかりきったことですけど、案外忘れがちです
それで、先回りして、話を進めますが、我々は一般に目が覚めてない存在なわけですが、とっくに目が覚めて、成すべき事を終えた存在も当然、想定されるわけです
それが、神々であり、仏菩薩なわけです
ですから、仏教は孤独に独りぼっちで歩むんではなくて、すでに目覚めた存在に助けられながら歩みます
勘違いしちゃいけないのは、助けられますが、歩むのは自分です
喉が渇いたら水のある場所は教えてもらっても、汲んで飲むのは自分です
世界の創造主が誰だとか、生死を司るのは誰だとか、仏教の文脈からは出てきません
世界とは、感覚器官で感じられた自分の心であり
自分の心が明らかになれば、それが悟りです
そういう意味で言えば、無神論です
自分の努力しか信じません
それで大日経には
如何が菩提とならば、実の如く自心を知るなり(目覚めとは何かと言えば、それはありのままの自分の心を知ることだ)、と説かれています
「素敵だなぁ」と思って花を眺めてると、素敵な人になってるんですよ

結局、実相というのは、自分の外側にあるんじゃありません
自分自身の中に、自分の感覚を通して形成されます
弘法大師的には声ですけど、波動と言いたいことろですが、とにかく止まっていない
微細な振動というか、運動を続けてると、言いたいんです
今は水でも、次の瞬間は蒸気だと
今は石でも、あっという間に粉になって、粘液になって、ガスになって熱になって、風になってる
今は人間でも、100年後には白骨か灰です
無常ですね
常なるもの無し
変化し続けています
その、内側にある感じられた世界を、自分自身ととらえるか
自分と無関係な外部世界ととらえるか
ここが大きな分かれ目になります
これは、考えてできることではありません
で、なぜ、その世界と一如になることが必要なのかということになるんですが
圓、頓でしょうねぇ
一番簡単で、手っ取り早く問題にアプローチする方法ですよ
これは、やって見せてもらわなければ納得できません
ま、お釈迦様はやってみせた、ということです
仏教では、過去七仏とか、三千仏とか言って、お釈迦様の他にも、無数の仏がいることを説いています
阿弥陀如来とか薬師如来、大日如来とかは聞いたことがあると思いますが、聞いたこともないような沢山の仏様がいます
それが、つまり、実相の中で暮らしてます
僕らの心の中に住んでるんです
それに気が付いたら、勝ち、と、まあ、簡単でしょ
仏教ではよく心を鏡に例えるんですが、鏡が世界を写してます
この鏡が自分じゃなくて、写っている世界が自分です
鏡はいずれ死んでしまいますが、世界がなくなるわけじゃありません
もともと鏡があっても無くても、世界は世界ですからね
ああ、それで、鏡と世界を分離することはできないのですよ
いっぺん洗面所に行ってやってみてください
鏡から写っているものを引き剥がせるかどうか

まだ最初の一行目も解説し終わってないですけど、いろんな言葉が出てきました
理---智
所観---能観
止---観
制感---観想
空観---唯識観
そして
世界---鏡
世界と鏡の関係が、仏教の考え方を簡単に現しているってことですね
般若心経で言う、色受想行識とか、仏教全般の苦集滅道とかも、つまりは、鏡の側の問題です
ついでに言えば、戒律も鏡の側の問題です
梵網経では、「自分はこれから仏になる」と思えば、全ての戒律が具足すると説きます
仏教には長い歴史の間、沢山の戒律フェチの坊さんがいますが、戒律の本質は単純です
輪廻転生は、鏡がするって解釈になるわけですが、この鏡の来し方行く末が問題の本質じゃなくて、写っている世界が問題の本質なんですね
仏教は、お釈迦様自身の転生物語のジャータカがあって、輪廻転生の上に成り立ってますが、あんまり「あなたの前世はどうだった、こうだった」と言ったりしないのは、転生はつまり、鏡の側の問題だからです
はっきり言って、鏡が無くても、世界は全然困りません
だから、まあ、前世は誰にもありますが、知らないでも全然かまわないと思いますよ
圓、頓ということに限って言えば
さてそれで
造境即中 無不眞實 ぞうきょうそくちゅう、むふしんじつ
造られた境はすなわち中なれば、真実にあらざる無し
中というのは中道で、極端でない、中庸の、いい加減の、苦でも楽でもない、といった意味で使われています
造境とは、鏡の中の映像といったことになるでしょうね
で、「造境すなわち中」、とは、圓頓でいきなり最初から実相に意識を集中するからです
だから、「真実にあらざるなし」ってことになります
なんでわざわざこんな説明を付け加えたのか、ですけど
「実相」が、つまり、鏡に写った、「造境」なわけで、「造境」は、鏡の数だけあって、全て違います
実相がそんなにいくつもあったら困るんですけど、しかたありません
国境を挟んで、敵と味方に別れたら、どちらかにとって正義は、もう一方では極悪です
人皆、自分だけのフィルターを通して世界を見、自分だけの道を歩みます
でも、鏡の側からでなく、世界の側から見れば、鏡同士の個別の問題は一つの本質の様々な局面に過ぎません
鏡の側にある死や苦痛も、そりゃ無いにこしたことはありませんが、世界の側からすればエピソードでしかありません
実相--->造境=中=真実
なかなか、ここの所は含蓄があって
普通に考えれば、「実相」は神だけにあるはずです
それが、鏡に写った、「造境」にも等しくある、と
で、つまり、汎神論です
多神世界が、仏教的な世界観です
ただし、こじつけみたいですが、
「実相」が腑に落ちないと--->のところがですね、繋がりません
いちおう、そういう説明でないと、アホな凡夫の存在が辻褄あいません
繋がらない「造境」は中であり真実ではあるんですが、それは自分だけの自己中、独善、妄想ってことになります
圓頓とは
初めに実相を縁じていれば(条件)
造境はすなわち中であり真実にあらざるなきものになる
ですね

圓頓章は仏教の2500年の歴史を、縮めて縮めて、無理して短く要約してしてますから、あまり、個々の字句にこだわらないほうがいいとは思います
「ここにこう書いてあるから、こうなんだ」とかね
やはり、自分の坐禅・瞑想の体験から、「ああ、この感覚のことをこんなふうに書いてるのか」とか「どうも、このへんが腑に落ちないな」とか、参考にするのが一番いいでしょうね
それでも、この圓頓章が、中国天台のみならず、比叡山から始まり、浄土宗、浄土真宗、曹洞宗、臨済宗、日蓮宗の淵源となり、高野山の密教とも相互に影響しあってきたのですから、「ややこしいから、わからん、無理」と、放り出してしまうのはもったいないです
仏教のエッセンスが詰まっています
まあ、ですから、簡単にわかったつもりになるのも、どうかとは思いますけど
さて、仏教のテクニカルタームは便利なんですけど、あまり使うと、堅気の方達に話が通じなくなりますので極力さけます
で
世界と鏡
ですね
ここのところが、一神教、たとえばキリスト教とかでは
神と人間
になるわけです
仏教には、インド古代からのウパニシャッドやヴェーダの要素が含まれています
たとえば、輪廻、多神世界、ヨガ、マントラなど
これらには、人類普遍の真実が含まれていると考えることもできますが、仏教は、いわゆるヒンドゥーイズムからも離れていきます
キリスト教的な「人間」とか、ヒンドゥーの「我、アートマン」を、仏教は幻影と見なすんですね
どうにも、体感的には、我々の肉体は個々別々に確固として存在してます
で、その人間が、神を信じる
これは、わかりやすい
神である「ブラーフマン」と人間の我である「アートマン」を、肉体のチャクラを通じて合一させる
まあ、理屈はわかります
そこのところを、仏教は、「一切皆空」、とか、「不可得」とか断じてしまいます
まあ、リアルに考えれば、今ここにある物や事は、100年後にはぶっこわれている可能性が非常に高いです
人間は、死んだら、灰か骨です
アートマンなど、蒸発してしまうかもしれません
どんな立派な鏡でも、いつかは、割れて砕けて、パア、です
それを言うなら、どんな、善行、人助けも、1000年も経てば忘れられて終わりです
刹那的な、私利私欲、享楽を、求められる時に求めなければ損、という考え方に、説得力があるようにも思えます
で、死後世界の物語やら、因果応報の勧善懲悪やら(それはそれでいいですけど)、拡大した世界観がどうしても必要になってきます
ま、ややこしい話が必要になるわけで、辻褄あわせるのに苦労するわけです
プロテスタント発祥の国のドイツでキリスト教離れが進んでるらしいですが(まあ、ニーチェの生まれた国ですから)
宗教が自己保存のために作り出してきた神話の辻褄があわなくなってきて、神話に妄想がかなり混じっていることが、バレてきてるんですね
それもこれも、鏡の存在を基礎にしてるからです
仏教のロジックは逆です
世界の存在が基礎です
鏡が割れても世界はビクともしません
仏教の中の神話的要素が崩壊しても、ロジックは残るでしょうねぇ
つまり
世界と鏡、の関係に対する考察は、鏡についての神話や説話が否定されても、世界についての認識は残る、ということでになるでしょう
世界を豊かにしたら、豊かになったまんま、傷つけたら、癒されるまで傷が残ります
世界は自分であり、見えたり感じたりすること全て、自分自身です
だから、周囲の人達や世界にいいことをするのは、自分にいいことをしてるのであって、悪いことをするのは、自分を傷つけていることになります
これが仏教の慈悲でありカルマです
自分の問題なんです
鏡と、そこに写っている世界を分離することはできません
見えている光景や、聞こえる音、匂い、味、この肉体の感触、などを含めて、自分とは、感覚器官によって感じられた、鏡の中の存在だということなんですね
眼耳鼻舌身と、それを感じるプロセスである色受想行識
それら全て、鏡の中の出来事です
だから、鏡も、鏡の中の出来ごとです
そこらへんまで徹底すれば、あなたも仏教徒です
圓で頓
完全で手っ取り早い、根本的な方法は
世界=鏡の中の出来事
と気が付くってことだ、というのが、仏教の立場ですね

鏡も鏡の中の出来事であり、それが「実相」だ
と
自分の身体感覚も、感覚器官を通して造られたイメージであり、それ以外に世界は無い
そこまではいいんですが、つまりは、「実相」とはなんでしょうか
世界であり、宇宙の万象であるのはわかりますが、だからどうだと言うのでしょうか
ここに缶詰があります
これを三人の人が見ています
見る角度が違うので、それぞれ別の缶詰の姿が見えます
でも、同じ缶詰です
見えている狭い角度の姿が世界の全てです
何のラベルかわかりませんが、これが世界の全てです
この三人が、これが何の缶詰が議論したら、缶があるということは合意するでしょうが決して意見は一致しないでしょう
ここで、神だけが、これが何の缶詰か決めることができる、と考えるか(一神教)
三人が別々の角度から見てる姿をイメージして、元の姿のイメージを再構成するか、です(仏教)
で、仏教の説明をしますが
つまり、見える前の姿をイメージすればいいわけです
感覚器官でとらえる前の姿が、本当の、ありのままの姿で、「実相」ということになります
鏡の中の出来事は「造境」です
このままでは、物事の一面にすぎません
自分の中にある、鏡の中の出来事に、愛着を持ち、執着し、こだわり続けていたら、真実を得ることはできません
「実相」は「造境」ではありません
しかし、「実相」が腑に落ちる、つまり、感じる前の世界に繋がれば、「造境」は真実となります
見えている、缶詰の姿にだけこだわっていたら、元の缶詰の姿はわかりません
と、まあ、理屈はそうなんですが、いったいどうしろというんでしょう
繋縁法界 一念法界 けいえんほうかい、いちねんほうかい
縁を法界につなぎ、念を法界にひとしくする
ここで、「法界」というのが、つまり、感じる前の世界です
縁を繋ぎ、念をひとしくする
というのが、止観なんです
瞑想ですね
でも、坐禅しろなんて、どこにも書いてありませんよ
心が繋がって、心が一つになる
以心伝心
心が通う
全く無垢な、純粋な、素直な、心と、心が通うんです
感じる前の世界は、意味があり、意志を持ち、語りかけています
生物だけでなく
大地、水、火、風、空など、全てが、心を持ち、語りかけています
そこには数知れない心がありますが、オーケストラのように混然と一如です
「法界」と繋がると、全てと一気に繋がります
圧倒的な、慈悲の感触です

「法界」と一口に言っても、それこそ2500年の間、あーでもない、こーでもない、と論じられてきたお題ですからね
まあ、簡単にかたづく話ではないです
ただ、繋がれば、世界(法界)=鏡に写った世界なわけで
勘違いから目覚めれば、「法界」は自分自身であるわけで、曼陀羅の諸仏は自分であるという、
これまたけっこうな理屈になるんですが
そこのところを
本覚讃(ほんがくさん)、という智証大師の作った偈文では
三十七尊住心城(金剛界の全ての諸仏が心に住んでいる)
と説いて、これを天台本覚思想と言いますが、本人が知らないでも、本来悟っている、完成された心を持っている、と考えています
ただ、この娑婆世界では、繋がっていくのに時間の経過が必要なわけで、実際は、ジワジワと繋がっていきます
で、その時、フォーカスする対象によって、各自の個性が出てきます
仏心に繋がる人もいれば、菩薩や明王、天部に繋がる人もいると
繋がっていく過程でも、自分の肉体感覚というか我執は残っているわけで、バランスを崩すと、悪魔になる可能性もあります
悪魔になって地獄を見ても、法界の側から見れば、ちょっとした遠足か道草といったところでしょうがね
圓頓章で、法界と繋がることと、念と法界を一つにすることを別々に言うのは、仏教の伝統の止観に合わせた言い方をしているのであって、実際は、同時というか、やってることは同じです
「具体的に、いったいどうすりゃいいの」という気の短い方には
光の瞑想をお勧めします
http://chohoji.or.jp/shousei/saloon.htm
ちょこっとでも、やってみんさい
コツは「微笑むこと」です
さて
この圓頓という考え方には、祈願というか、個別の願望成就の方法は書かれていません
ま、圓頓は仏教のエッセンスであり、基礎の基礎ですから、各論は別のところでやることになります
各人各様の都合や、個人の経歴はどこまでも付いてまわるので、この圓頓から、いろーんな解釈が派生するということだと思いますが、仏教の正しい祈祷法や回向法は圓頓で説明がつくということでもあります
繋がる
一つになる
心が通う
など、ま、基本だということです

ここで重要なのは、「法界」を無条件に信用してるってところなんですが
これはですね、「法界」には我がないからです
仏教的には、我とは「鏡に対する執着」です
つまり、自分がいるという素朴な感覚ですね
で、他人がいて、沢山知らない人達が生きているという、ありふれた感覚です
しかしながら、見える前の世界、鏡に写る前の「ナマ」の世界は、鏡じゃないわけで、我から切り離されています
だから、「法界」は善悪、正邪、損得、苦楽、好き嫌い、愛と憎しみ、私利私欲、など、人間生活にまつわる価値観とは無縁です
実際のところ仏が慈悲深い、とは、ものの例えで、我のない心のことをそんなふうに例えるんじゃないでしょうか
ですから、法界には因果律があるのですが、この法界の因果応報には勧善懲悪的作用はありません
なにせ、我がない心の作用ですから
ハンデを負った人生も卑下することはありません
ちょっと、人と違う経験をしてみているだけのことです
逆に、人より勝れていると自他共に認められていても、威張ることもないです
ちょっとばかりラッキーだったというだけのことです
それでですね、人の存在は幻想ですから
神と人の、相対する関係を前提とした世界観は、仏教では採用しません
鏡の強化、拡大、装飾などは、問題の本質にはなりません
鏡はいずれ、灰になります
ここのところに気が付くまで、輪廻は終わりません
まあ、時間は永遠にあるんですから、気の済むまで輪廻することになります
それで、仏教的には、神様や偉大な霊とおつきあいはしても、目標にはしません
目標はあくまで圓頓です

一色一香 無非中道 いっしきいっこう むひちゅうどう
ひとつの色、ひとつの香りも、中道にあらざるなし
ちっぽけな、目に見える物、ちょっとした香りも、中道である
中道とは、中庸、正しい道筋、真実といった意味で使っています
「法界」と繋がれば、なんでもかんでも、見える、聞こえる、香り、味覚、触感、すべてが真実です
それで、禅問答で
「犬の糞に仏性はあるか?」
という質問に
「ある」と答えたら、屁理屈をこねたってことで、警策でシバク
「ない」と答えたら、わかっていないとシバク
てなことになります
「法界」になれば
宇宙の全てに意義がある
意味の無いものは無い、全てはメッセージということになります
法界にとっては、なんでもかんでも、中道で真実です
法界には、苦痛や不善を感じる我がありませんから、全てが肯定されます
じゃ、困っている人を誰が助けるんだ、ということになるんですが
ここで、菩薩が必要になるわけです
菩薩とは
サンスクリットの bodhi と sattva がくっついて出来た言葉で、bodhiが目覚めたという意味で、sattvaが有情、情ある者という意味で、あわせて、目覚めていながら情がある者、衆生を救うため完全な悟りの世界にいかない者、をさします
あるいは、お釈迦様や阿弥陀如来のように、誓願がある仏様もいます
もともと、慈悲とか慈善を仏教はあまり熱心に説かないのです
日本天台の伝教大師からでしょうね、慈悲を仏教の中心に据えたのは
それまでは、成就仏身、菩提、悟りであるとか、弘法大師だと悉地成就です
法界になることが先決で、慈悲は派生する問題なんです
それで、まあ、社会の改良とか、不正の追放、正義の執行など、仏教は、そんなに熱心ではありません
そんなことほったらかして、法界になることに集中します
出家し、寺にこもって、瞑想し、経典の読誦研究にあけくれる、ってことになります
もともと、お釈迦様の時代、仏教は出家主義でしたが、それは、社会全体が豊かになり余剰な食べ物が生産できるようになってきたからです。つまり、働かなくても食べていける。
当時、ガンジス川流域では米を作っていました。今の日本米の系統の短粒米です
土地の面積あたりの収穫量が飛躍的に増えたのです
古代インドでは存亡をかけた大戦争が続き、お釈迦様の一族であるシャカ族はコーサラ国に滅ぼされます
大国のコーサラ国は小国のシャカ族から政略結婚で妻を迎えますが、じつは、シャカ族は奴隷の娘を王姫と偽って嫁がせたのです。そして生まれたのがビンビサーラ王です
出生の秘密を知ったビンビサーラ王は怒り狂い、シャカ族討伐に向かいます
ところが、その道の途中の木の下で、お釈迦様が瞑想しているではありませんか。ビンビサーラ王は、深く仏教に帰依し、お釈迦様が、元シャカ族の王子から出家したのを知っています。いったん兵を引きますが、憎しみは消えず、2度、3度と兵を向けます。そのたびに、お釈迦様に出会って、兵を引くのでした
しかし、4度目に兵を向けた時、お釈迦様はいませんでした
そして、シャカ族はコーサラの大軍に皆殺しにされ滅亡しました
ここから、「仏の顔も三度」という話ができました
お釈迦様が、アーナンダなど元シャカ族の青年を多数出家させたのも、このシャカ族の滅亡がわかっていたからだ、とも言われています
さて
余剰な食料が蓄えられるようになって、戦争と瞑想が盛んになったということですね
現実問題として、生きている限りは肉体を捨ててはいないわけで、我々の最善の選択肢は、菩薩、bodhisattva、「目覚めているが情がある者として生きる」ということでしょうかねぇ
今でも、大陸のインド、タイ、ミャンマーなどでは、出家にあらざれば僧にあらずで、大きな国際的仏教行事なども、日本人の妻帯した坊さんは僧侶の席に座らせてもらえません
中国も出家主義ですね、まあ、同席はさせてもらってますが
これはこれで、見識ですが、未来に続いている道は、bodhisattvaだと思いますよ

圓頓章の概略は最初の二行で説明しつくされています
「完全で素早い」ことを目指しているんですから、結論から書いてしまうんですね
圓頓者。初縁實相。造境即中。無不眞實。
繋縁法界。一念法界。一色一香。無非中道。
完全で素早い方法
初めに「法界の心」につながれば、心の鏡に写し出された世界は真実そのものとなる
「法界の心」につながり、ひとつになれば、すべては真実となる
「法界の心」は、無条件の大慈悲であり、菩提心であり、無上正等正覚であり、自心の源底であり、迷いから目覚めた本当の自分自身です
自分が本当の自分になるだけのことですから、全く簡単なことです
ただし、条件があります
つながる、ひとつになる
ということ
悪いことをするな、善いことをせよ、というのは仏教の基本的戒律ですが、そんなことはどこにも書いてません
捨身苦行せよ、なんてこともありません
なんってたって、圓頓ですから
この「つながる」ですけど、これをサンスクリットで言うと
yoga です
英語のyoke(船などを係留する)という単語の語源です
古代インドの各種ヴェーダで確認できますが、人類でもっとも古くからある瞑想法です
ヴェーダでは、神と人との合一、というロジックなんですが、仏教に取り入れられた時には「真実と自心の融合」に作り替えられました
偉大な個性と、弱小な個性が「つながる」というイメージは、仏教からすると、自分という執着にしがみついたままで、我があります
仏教では、我という執着が捨てられないかぎり、苦痛の淵源になると考えています
我(つまり鏡)も鏡の中の姿です
それで、なにか崇高な対象を崇めて自分を豊かにする、という発想は仏教のなかでは、方便であり、主たる感心事ではありません
お釈迦様が入滅して、1000年くらいたつと、そうした厳格な脇目を振らない考えかたから、仏教を応用して現実的社会的な願望を成就する技術が盛んになります
それが、密教です
密教はヴェーダからの伝統が色濃くて、yogaだらけです
で、密教では、こちらの意図に応じて対象を決め、法界の中の存在を選択してつながることができます
法界の中では、砂糖がお湯にとけるような混ざりかたでなく、オーケストラの音楽のように、様々な存在が個性をもちながら一つに解け合っています
仏の名前だけでも3000以上あります(三千仏名経)
これは「例え」で、無数の仏がいて、しかも、増え続けています
「法界の心」とつながると、自分も、その存在達に仲間入りします
つまり、今、凡夫の我々は、大金持ちの一人っ子なんですが、気が付いていない状態だと、これは法華経に書いてあります
個性をもったまま解け合いますから、今、皆さんがなさっていることは、一つ残らず、ご自身の財産となって役立つことになります
僕は、法界を豊かにするために、様々な経験や、迷いや、自由があるのだと考えています

こうやって書いてみると、けっこうややこしいですね
インドでお釈迦様が説法を始めてから、もう2500年
密教が整備されてから1500年
圓頓章が作られて1400年
比叡山が開創されて1200年
技術文明は目に見えて進歩したかもしれませんが、人間性は相変わらずかもしれませんね
この圓頓章は摩訶止觀(まかしかん)の序文の一節です
書いたのは、天台大師の弟子の章安
天台大師の講説を筆録しました
天台でもっとも基本になる講説の法華文句、法華玄義、摩訶止觀を天台三大部と言います
法華文句は法華経の逐語的説明
法華玄義は法華経的世界の解説
摩訶止觀は坐禅の実践方法の解説、です

章安大師画像 長保寺蔵
561〜632。灌頂、後に号して章安大師。幼時父を喪い、7才で出家。23才で天台大師の門下となる。天台三大部(法華玄義・法華文句・摩訶止観)、五小部(観経妙宗鈔・金光明経文句記・同玄義拾遺記・別行観音玄義記・別行観音義疏)などを筆録。
http://www.chohoji.or.jp/TENDAI/santaibu/001/04.txt
ここの上から50行目くらいかな、P:2aのあたりが圓頓章の部分です
ですから、基本的には、圓頓章は坐禅の実習法の要約です
坐禅の実際のやり方の解説は、摩訶止觀で完成されて、あとは摩訶止觀の要約であるとか、摩訶止觀の部分的解説しかありません
摩訶止觀は空前絶後なんです
それだけ、坐禅はシンプルで、普遍的な方法だとも言えるわけですが、摩訶止觀を本格的に読みこなすには、今なら大学院にでも行って研究するしかないでしょうね
岩波文庫に書き下しがありますが、絶版してます
圓頓章の部分だけでも、ここで16回やって、まだ2行しかきていません
たいへんな密度で、ぎっしりと坐禅が解説されているのです
それで、本格的に圓頓を実践するには坐禅をすることになります
天台宗では、この坐禅をまたパワーアップした法華三昧行法(ほっけさんまいぎょうぼう)を今実践してます
21日の間、法華経を一日6回読んで、その間に、一日4回坐禅する
という、寝るヒマのない修行なんですが、今でも比叡山では、毎年何人かこの修行をする人がいます
http://www.chohoji.or.jp/TENDAI2/2data/01/37.txt
それをまた縮めたのが法華懺法(ほっけせんぽう)で、これは天台寺院なら、日常的にしてます
経典を読誦する法要で、40分くらいで一座できます
平安時代は皇族や貴族も熱心に修しました
http://www.chohoji.or.jp/TENDAI/huroku1/10.txt
法華懺法の一番最初に、総礼伽陀(そうらいかだ)があります
我此道場如帝珠 十方三宝影現中
我身影現三宝前 頭面摂足帰命礼
がしどうじょうにょたいしゅ
じっぽうさんぽうようげんちゅう
がしんようげんさんぽうぜん
ずめんせっそくきみょうらい
我がこの道場は帝珠のごとし
十方の仏法僧がその中に影を現す
我が身もまた仏法僧の前に影を現し
頭面を足につけ帰命礼す
つながったからには、過去現在未来、東西南北上下の諸仏諸菩薩や神僧が目の前に現れます
これは、目に見えなくても、全然かまいません
目が覚めていないから、そこにいるのに気が付いていないだけです
帝珠のごとし、とは、帝釈天のもっている珠玉が、お互いを照らしあい、一珠の中に全ての珠玉が写りこんで、宇宙の森羅万象を写しているのにたとえています
法華懺法では、眼前に影現する三宝(仏法僧 ぶっぽうそう)に我が罪を懺悔します
まあ、しかし、昔から楽をしたいと考えた坊さんはいたわけで、摩訶止觀を全部読まないでもなんとか意味の通じる部分を探して、圓頓章だけ読めばなんとかなる、ということになりました
意味がわかって読んでる人がどれほどいるかわかりませんが、なにか、声を出して読むだけで不思議な感応がありますから、それでいいんでしょう

法界とつながると、自分の心が法界となって、全てが真実となる
まあ、言葉で書くとそういうことなんですが、これでわかったつもりになられちゃ困ります
己界及佛界 衆生界亦然
こかいぎゅうぶっかい しゅじょうかいやくねん
己界および佛界と衆生界もまたかくのごとし
法界を三つに分けるんですね
己界、自分の世界です
どこまでも、己界は己界です
死んでも、輪廻転生しても、法界に行っても
佛界、大雑把に、諸仏諸菩薩や神僧のいる世界をひとまとめに佛界としておきます
衆生界、生きとし生ける者達の世界
他人、他の存在の世界です
佛界にまだ行っていない自分以外の存在です
ですから、目覚めるまでは己界は、衆生界のなかにあります。
己界、佛界、衆生界、合わせれば法界全ての存在を説明できます
自分は自分、他人は他人なんです
どこまでも
それが、法界ではつながっています
解りやすく言えば、「心が通う事」、それが一番大事です
密教の加持は、じつは、この「己界、佛界、衆生界」の応用です
本尊を念じ、己界の中で、苦しみのある衆生界に佛界を繋ぎます
普段は佛界を自分に繋ぎます
ここが不思議な感じのするところなんですが、己界と佛界を繋ぐと、自然に、意図しなくても、衆生界に影響が及ぼされます
これを
「真言行者、座を立たずして一切の仏事をなす」
と言ったりしますが、ふだんから心の通う仲間、身内、知り合い、などは、考えなくても繋がっているんでしょうね
「一人出家すれば、九族天に生ず」
とも言います
と言うか、繋がっているのに気がついていない状態なんですから、気がつけば、もっと具合良くなる、ということでしょう
それで、うまく繋がれば、霊験があります
霊験とは、法界の因果関係です
ですから、現れるのに、それなりの約束事があります
仏には仏の都合もあるわけで、機械的な作用反作用ということにはなりません
和光同塵(わこうどうじん)と言って、温かい光が降り注いでも、地面の上の事情にも左右されます
端折って言いますが、簡単ではありません
しかし、必死になれば、見よう見まねでもできます
素の自分になって、念じるだけのことですから、慣れればなんとかなります
反復すれば、だんだん繋がりやすくなってきます
才能や体質もあるかもしれませんが、古来仏教では、どんな些細なことでも全て無駄にならない、としています
片手を上げて礼拝する、ちょっと会釈する、線香を一本立てる、一言「南無」と言う、砂遊びで仏像をつくる、ふざけて袈裟を着て踊る、などなんでも、忘れてしまっても全て仏縁になります
密教では、繋がる方法を身口意(しんくい)の三密にわけて考えます
本尊と、印(身密)と真言(口密)と観念(意密)が一致すれば、自分と本尊が一致します
人間活動は、とどのつまり、身口意の三つ以外ありませんからね
三密加持すれば速悉に現る(弘法大師)
「圓で頓」とか、「速かに悉く」、とか、同じようなことを言ってるんですよ
仏教の真理が、そういくつもあるわけじゃありませんからね
印は、手の指の組み合わせですから、まあ、見て真似ることもできます
真言は、「アビラウンケン」とかの言葉ですから、書いてある文字を読めば言えます
ただ、観念ですね
本尊と心が一致しなければならないわけです
これが、普通できませんから、簡単に霊験は起こりません
圓頓は、この観念の部分の解説になります
ですから、圓頓がわかれば、密教もわかります
密教は伝授の道筋を極めて重視します
これは、秘訣や秘伝を教えるってことじゃなくて、「師僧さんと弟子の心が通う」ということです
その、もとをたどると、お釈迦様に行き着きます
ですから、厳粛な儀式や手続きが、どうしても必要ということじゃありません
ただ「心が通うこと」は絶対に必要です
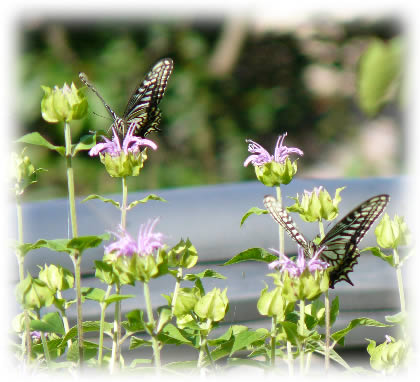
陰入皆如。無苦可捨。
無明塵勞。即是菩提。無集可斷。
邊邪皆中正。無道可修。
生死即涅槃。無滅可證。
おんにゅうかいにょ むくかしゃ
むみょうじんろう そくぜぼだい むしゅうかだん
へんじゃかいちゅうしょう むどうかしゅ
しょうじそくねはん むめつかしょう
陰入みな如なれば、苦として捨つべき無く
無明や塵勞はすなわちこれ菩提なれば、集として断ずるべき無し
邊邪みな中正なれば、道として修するべき無く
生死すなわち涅槃なれば、滅として證するべき無し
ここでは、仏教の基本的な教えである苦集滅道(くしゅうめつどう)の四聖諦(ししょうたい)がでてきます
順番が苦、集、道、滅になっています
苦しみを
生老病死(しょうろうびょうし)に分類し
生の苦しみを、細かく分けて
怨憎会苦(おんぞうえく) 憎しみあう相手と会う苦しみ
愛別離苦(あいべつりく) 愛する人と分かれる苦しみ
求不得苦(ぐふとっく) 求めているのに得られない苦しみ
五薀盛苦(ごうんじょうく) 感覚器官による、暑さ寒さ、空腹、眠気などの苦しみに分類して
生老病死を四苦(しく)、全部合わせて八苦(はっく)と言います
これらの苦しみの原因を集とします
苦しみを緩和、あるいは解決するための実践を道と言い
その結果苦しみが無くなるのを滅とします
仏教でいう四苦八苦は、生きている限りは、逃れることのできないものだとされています
仏教が始まってから2500年経ちますが事態は変化してません
老化は避けられません
病は文明の進歩でかなり対応策も発達しましたが、病気になること自体はなかなか避けられません
死は誰も免れません
怨憎会苦、憎しみあう相手と会う苦しみ
愛別離苦、愛する人と分かれる苦しみ
求不得苦、求めているのに得られない苦しみ
これも、相変わらずですね
五薀盛苦、これはいろいろ言うんですが、感覚器官による苦しみですね、感覚器官が鋭敏過ぎるのも苦痛として考えています
ま、いずれにしろ、五感が苦しみを感じることは、無くなりませんね
それを解決しよう、というんだから、仏教は人類永遠のテーマになるわけです
お釈迦様は、解決した、と宣言してます
あれ?
我々の人生は相変わらずなんですけど
圓頓章では
無苦可捨
無集可斷
無道可修
無滅可證
苦として捨てるべき無く
集として断ずるべき無し
道として修するべき無く
滅として證するべき無し
と、苦集道滅を「無い」と言っています
無いってことは、問題にならないわけで、解決したことになるんですが、実際は、ありとあらゆる、苦悩、矛盾、貧困、戦争、嘘、悪逆、がいたる所にあるわけです
これ結局どう解釈するかですけど
苦集道滅は鏡の世界にあるんです
我がある限りなくなりません
法界には苦集道滅がありません
我が無いからです
つまり、法界と繋がると、苦集道滅から解放されます
法界と繋がり一つになれば
一切皆、真実で、一色一香皆、中道ですから
苦も集も滅も道もありません
ですから、仏教では、現世の問題を解決するより、法界と繋がることを優先します
法界と繋がることを、根本的解決、と考えています
制度としての出家は、お寺に入って精進する、ということになりますが、ホントのところは、「法界至上主義」とでも言うんでしょうね
現実的な問題に係わるのを避けて、瞑想に明け暮れようとします
それで出家が、単なる自己満足や現実逃避であるという指摘になるのですが、どうも、そこがちょっと違うような気がします
自分が法界と繋がることで、有縁の衆生も法界に繋がっていきます
知る限りの世界が、法界となります
具体的には、私利私欲の無い世界になっていきます
単純に言えば、法界とは我の無い世界です
ですから、全てが法界になると、無我の世界になるという理屈
それで、現世利益とか病気平癒、家内安全とかもろもろ、
仏教の御利益とは、無我によってもたらされる果実
ということになります
まあ、魔法じゃないんです

「無我」なんですけど
実際は、仏教はあんまり「無我」という言葉は使いません
その、なんと言いますか、冷たい感じじゃないんですよ
燦然と生命が輝いている感触です
「無我」だから、ボケーっとしてたらいい、なんてもんじゃありません
ですから、「空」とか「如」とかの言葉になります
まあ、このへんは感じてもらうしかありません
いっしょに手を取り合って輪になって踊りたいような、はじけるような歓び
ありがたくて、もったいなくて、ただただ涙がながれる大慈悲の感触
深遠な安らぎ
そんなものが、一緒になったような、圧倒的な感覚です
で、法界とつながると、それが、縁のある人達につながっていくと
陰入皆如。無苦可捨。
おんにゅうかいにょ むくかしゃ
陰入みな如なれば、苦として捨つべき無く
陰は仏教用語です
サンスクリットでsukandha
蘊とも訳します
色受想行識のことです
感覚器官で感じる対象が、色
それを、取捨選択して感じるのを、受
そこから、ある印象が生じるのを、想
印象が刻々と変化するのを、行
そこまでまとまると、なんらかの意識が生じます、識
この色受想行識が、みな「如」だと言うんですが
ここで言う「如」は、如来の如で、これがまた仏教的には深いんです
鏡にうつった姿なのだが、ありありと存在してる、それで、「来るが如き」者という意味で如来と言います
般若心経で「色即是空、空即是色」とか「五蘊皆空」とか言いますが
「陰入皆如」は同じような意味になります
法界の側から見れば、全ての鏡の中の現実は、如であり、空です
ですから、苦として捨てるべきものが、どこにもありません
「え、病気が治るんじゃなかったの」
「あれ、金持ちにはなれないの」
と思ってる、あなた
そういうことも実際はありますが、約束はできません
法界には、「法界の因果」がありますから
ただ、これだけは言えます
なにがあっても、おろおろ取り乱さない
落ち着いて、腹を据えて事に当たれるようになります
戦国時代の武将が坐禅をたしなんだのは、そのへんが理由でしょうね

「法界の因果」について
これ、物理学とか化学や数学の法則と言ってもいいんじゃないかと考えてます
全てが解明されたわけではないが、解明されつつあると
霊験や奇蹟も、最終的には、「説明のつく事」になるのではないでしょうかね
仏教の唯識論的な解釈をすれば、心の領域も物質世界も、全て識作用であって、物理・化学・数学なども識作用の一部という理屈になります
境界線は、心と物質の間ではなく、観察される前の世界(実相)と、心に認識された世界(造境)の間にあります
僕は、実相と造境の境目が、量子論のSuper Position だと考えてますが、まあ、あと100年もすればわかってもらえるかもしれません
実相と造境は、実際は、同じ心が目覚めているか、目覚めていないか、の違いにすぎません
世界の全ては識作用です(三界は唯心の所現 華厳経)
「法界の因果」とは、ですから、「識作用の法則」であり、自分の心の中の出来事ということになります
一神教では、そこのところをどうしても、「神の意図」と考えたくなるんですが、仏教から言えば、「神という概念」が気に入らないんです
「神という概念」は鏡の中の世界のことですから
それで仏教では「如来」という言葉を使います
キリスト教の「神」やイスラムの「アッラー」を仏教的に「如来」と呼んだものかもしれないなぁ、と考えたりします
ただし、一神教では、人は絶対に神にはなりません
それを、仏教は、「速やかに仏身を成就する(法華経 自我偈)」、と言ってるんですから、僕は、素朴に、仏教ってスゴイと思ってます
圓で頓だって言うんですからね

無明塵勞。即是菩提。無集可斷。
むみょうじんろう そくぜぼだい むしゅうかだん
無明や塵勞はすなわちこれ菩提なれば、集として断ずるべき無し
いろんな仏教用語が出てきます
無明(むみょう)
目覚めていない状態の根本原因のことを言いたいわけですが、言葉自体の解釈は長い歴史の間に様々あります
つまり、全く繋がっていない状態なわけです
それで、なぜ繋がらないか、それがわかれば苦労しないんですが、とりあえず、無明という言葉で表現されることになりました
塵勞(じんろう)
煩悩の異名
目耳鼻舌身意で感じる色・声・香・味・触・法を六塵と言い、それを塵とします。感じることが心の迷いの原因という考え方ですね
煩悩によって心が疲労し倦怠するので、労と言います
菩提(ぼだい)
サンスクリットでbodhiです
目覚めた、という意味になります
集は、苦の原因なんですが、無明や煩悩は菩提だから、苦の原因として断つべきことが無い、と
法界には苦しむべき我がありませんから、その原因もない、という境地
ですから、法界の霊験には、条件や理由は必要ありません
仏や菩薩の御利益には、賽銭を上げろ、とか、善行をなせ、とかの前提条件はありません
賽銭を上げたり、善行をなすのは、本人の功徳になるだけのことです
仏教経典で、仏の慈悲に、何か倫理的な実践が条件に書かれたものはありません
たとえば、観音経などでは、「念彼観音力」で、ただ観音の力を念じることが求められるだけです
阿弥陀仏の極楽に行くには、念仏するだけです
お釈迦様は、自ら無条件に念じています
毎自作是念 以何令衆生 得入無上道 速成就仏身(自我偈)
つねに自らこの念をなす いかにして衆生をして無上道に入らしめ 速やかに仏身を成就せしめるかと
親孝行したから観音さんが動くとか、慈善団体に寄付したからお地蔵さんが助けてくれるとか、倫理的な強制や条件は無いです
親が子を愛するのに、なんの条件もないのと同じことです
全く、すっきり、はっきり、繋がって一つになれば、圓で頓で法界になります

圓頓章が書かれた時代
中国は、大戦国時代でした
三国志の時代を経て、五胡十六国時代に至り、南北朝時代になっても、戦争また戦争で、500年以上に渡り様々な国が興り滅びました
圓頓章を講述した天台大師の時代(538ー597)、は年表で見ると、いったいどの国がどうなっていたのかわからない位、混乱しています
飢饉もあり、天台大師は、ドングリの実を拾って食べ、修行を続けたこともありました
「苦も無く、苦の原因も無い」、という境地は、決して平和ボケの妄想ではありません
昔の人の偉いところは、そういった何もない戦乱の世に、道を求め、厳しい修行にあけくれたことです
ゆとりがあるから道を求めたんじゃありません
おそらくは、現代と比べられない位、人々は死に近かったと思います
なにかするのに命懸けはあたりまえ、生命保険も年金もありません
手っ取り早い現世利益は、きっと当時の人々が求めていた救いとは別物でしょう
まあ、世界一平均寿命が長く、飽食で平和ボケの国にいたら、道を求める必要を感じなくて当たり前でしょうねぇ
圓頓章は、結局、
「自分の中に生きる意味の答えを見いだす方法」です
どこにも、誰かに聞け、などとは書いてありません
それと、何かを信じろ、とも書いてありません
古代の人々が、生命の危険と隣り合わせのなかで、単刀直入に真実に触れようとした成果です
富、権威、名声、そんなものは全く必要ありません
壮麗な伽藍もいらないんです
まあ、僕とこは、本堂・搭・門と国宝で、境内15000坪が国史跡ですけど、はっきり言って、無くてもなんとかなります
せっかく立派なものを残してくれたんたんだから、大事にしなきゃなりませんがね
毎日、文化財の中で暮らしてる僕が言うんだから、しゃれでも、思いつきでもありません
真実は、自分の中にあります

邊邪皆中正。無道可修。
へんじゃかいちゅうしょう むどうかしゅ
邊邪みな中正なれば、道として修するべき無し
片寄ったこと、邪悪なことも、みな、中庸で正しいことであるので、仏教の修行として歩むべき道は無い
これは、まあ、なんの説明もなくここだけ取り出して、自分の都合のいいように解釈しちゃいけないでしょうね
実相とつながって、一つになれば、という条件のあるのをお忘れなく
法界には我がありませんから、当然、道を歩むということもありません
ま、理屈ではそういうことです
これですね
「正しい事をする」、ということと、「悪い事をする」ということの、仏の慈悲からの距離はいっしょなんです
正しい事をするから、仏の慈悲があり、悪い事をすると慈悲が無い、ということじゃありません
仏の慈悲には、何の条件も無いんです
親が子を愛するように
それと
「正しい事をしてる」という意識があるうちは、ホントじゃありません
法界とつながって、一つになって、当たり前の事をする、というのがホントです
法界には我がありませんから、善悪正邪損得軽重はありません
ですから、法界から見て当たり前は、それを鏡の側の世界から見ると、ひょっとして、極悪かもしれないんです
ちょっとわかりにくい所ですが、善行をいくら積み重ねても、法界とは繋がりません
逆に、法界と繋がっていると、どんなに悪逆に見えることをしても、繋がりが切れません
ただし
善因善果、悪因悪果、はあります
万に一つの例外もありません
でも、それは、鏡の世界のことです
法界と繋がるかどうか、切れるかどうかとは関係無いんです
王侯貴族が福徳を積んで贅沢三昧をしながら法界と繋がるのと
極悪人が身から出た錆で裁判にかけられ、反省して監獄の中から法界と繋がるのと
どちらも、繋がることに違いはありません
仏教には戒律がありますが、法界から見た当たり前を規則にしただけのことです
ですから、法界と繋がっていれば、なんら意識せずとも戒律が守られています
その逆に、戒律をいくら守っても、法界とは繋がりません
鏡の世界で評価されても、法界と繋がることと関係は無いのです
簡単に言えば、偽善やスタンドプレーはだめよ、ということです
己の徳行を数え上げて自慢しよう、などという気持ちでは法界とは繋がりません
繋がっていれば、自分のしたことを淡々と述べるだけです
こういうことは、外からはわかりにくいですが、きっと、輝きが違うと思いますよ

現行の天台宗の戒律をご紹介します
下記のようなことを、比叡山の戒壇院(国宝)で授かります
天台宗の戒律
正授戒
攝律儀戒を守り
道心ある人となります
攝善法戒を守り
能く行い能く言う人となります
攝衆生戒を守り
一隅を照らす人となります
戒
不殺生戒
あらゆるものの命を大切にいたします
不偸盗戒
いかなるものでも無断で自分のものといたしません
不邪淫戒
人の道にはずれた行いはいたしません
不妄語戒
うそ いつわりは申しません
不邪見戒
自分勝手な考えを慎み 正しい分別に従うようにいたします
正道(聖い法の道)
第一
正見 正しい見解をもつこと
第二
正思惟 正しい意志をもつこと
第三
正語 正しい言葉で真実を語ること
第四
正業 正しい行為をすること
第五
正命 正しい生活を充実すること
第六
正精進 正しい努力をすること
第七
正念 正しい動かざる心をもつこと
第八
正定 正しい精神を確立させること

円頓戒本尊像 長保寺蔵
絹本著色 明治21(1888)年
お釈迦様が本尊で、左右前方に比丘形の文殊・弥勒菩薩が配置されます
長保寺にある画像には、上部に月輪、日輪などの神秘的な図形がありますが、それぞれに意味が込められています
これが、比叡山で行われてる圓頓戒です
戒律としては極めて単純なものです
しかし、これだけのことでも、書かれたとおり、ちゃんと守れる人は、聖人です
絶対に、ちゃんと守れません
それで、布薩(ふさつ)と言って、いわば反省会をすることになっていますが、天台宗では、比叡山の伝教大師の御廟の待真僧(じしんそう 12年籠山行をしている阿弥陀仏を感得した行者 感得するまで毎日三千回五体投地の礼拝をする)さんだけでしょう、ちゃんと布薩をしてるのは
梵網戒經に基づいて布薩を行います
http://www.chohoji.or.jp/TENDAI2/2data/01/29.txt
汝是當成佛。我是已成佛。
常作如是信。戒品已具足。
汝(修行者)はこれ、まさに仏になる、我(釈迦如来)はこれ、すでに仏になれり
常にかくの如き信をなせば、戒品はすでに具足す
と、まあ、自分がこれから仏になるのだと確信すれば、戒律は自ずと備わります
戒律に書かれていることを、一々ちゃんと守ろうとすると、たぶんノイローゼになるでしょう
しかし、圓で頓に法界と繋がれば、意識せずとも、戒律に則った生活ができるようになります
あれをするな、これをするな、ではなくて
法界と繋がれば、それでいいのです
それにしても、これだけ立派な戒律があるのに、なんで、クソ坊主が多いんだ、と思うかもしれません
そりゃそうなんですが(^^;)
戒律があっても守れないんですから、無ければもっとめちゃくちゃでしょう
道路交通法のようなもんです
速度制限があっても取り締まりが無ければ、けっこう誰でもかなりのスピードで走ります
スピード違反やちょっとした反則はだれでもしたことがあるでしょう
それでも、道路を走るのに、全く何の制限も規則も無ければ、大混乱になります
どうせ守れない戒律なら無いほうがいい、という考え方は、道路交通法が無い道を自動車が走り回る社会を想像してみたらいいんじゃないですか
残念ながら、なんのルールも無い社会では、正面衝突だらけになって、まともな生活はできなくなります
ですが、ずっと法律を考え考え、車の運転をしてるわけじゃありません
慣れてしまえば、無意識に運転できます
同じ様に
法界とつながれば、ルールに縛られなくても、うまくいきます
論語
子曰はく、
「吾十有五にして学に志し、
三十にして立つ。
四十にして惑はず、
五十にして天命を知る。
六十にして耳順ひ、
七十にして心の欲する所に従ひて矩を踰えず。」と
先生はおっしゃった、
「私は十五歳で学問に志し、
三十歳で自立した。
四十歳で狭い枠にとらわれないようになり、
五十歳で天命を知った。
六十歳で人の言うことを逆らわないで聴けるようになり、
七十歳で心の欲するままに任せても限度を超えなくなった。」

生死即涅槃。無滅可證。
しょうじそくねはん むめつかしょう
生死すなわち涅槃なれば、滅として證するべき無し
法界から見れば、鏡の世界の生死は涅槃と同じことで、苦しみを終焉させるため達成することなど、どこにも無い、という境地
涅槃とは、仏教用語ですね
一神教社会では、まったく理解できない概念だと思います
まあ、今の日本人にも、なかなか理解してもらえないと思いますが
簡単に言えば、涅槃とは法界のことです
煩悩を滅し尽くした世界、煩悩の炎を吹き消した世界
ということで、何もない無味乾燥の退屈な世界という誤解がありますが
常・楽・我・浄、を涅槃の四徳と言って、
「永遠で楽しく自分という意識は失われず清らかである世界」です
法界が、常・楽・我・浄の世界だということです
今、目の前のパソコンのモニターをご覧になってると思いますが、この、見えてる、感じてる世界がすなわち、涅槃だと
だから、この世界がお釈迦様の心だ、と気が付いていないんだと
まあ、なるわけです
涅槃という、どこか遠い国があるわけじゃありません
涅槃については、涅槃経にいろいろ書かれています
http://www.chohoji.or.jp/TENDAI2/2data/01/43.txt
涅槃経で書かれているテーマは二つあります
「如来常住」にょらいじょうじゅう
お釈迦様は不滅である
「一切衆生悉有仏性」いっさいしゅじょうしつうぶっしょう
全ての生きとし生ける者は、いつか仏になる
お釈迦様は悟りを開いてから50年にわたって説法を続けましたが、全ての生き物が仏になる、というのは、涅槃経で遺言しているだけです
最後の最後まで、はっきり言わないのです
そのため、仏教教団では「仏性の無い人間がいる」という説が、かなり根強く主張され続けました
つまり、「仏になれる人もいれば、なれない人もいる」という説
僕的には、「仏になれない人(あるいは霊的存在)はいる」、だけど、「なろうと心に誓えば、仏になれるようになる」ってことだろうなぁ、と考えてますけどね
ボンヤリと時間が経てば仏になるわけじゃありません
誰かの手助けも必要でしょう
甘くはないと思いますよ
それで
「如来常住」とは、涅槃に入ったのだから、法界と同化したわけで、つまり、目の前のパソコンのモニターが、お釈迦様です
あなたの手のひらも、コンセントに流れる電気も、etc
「一切衆生悉有仏性」とは、だれでも圓で頓に法界になれるんだ、ということですね
これは、ですから、一神教世界では絶対に言わないことです
生殺与奪の力を持って君臨する全知全能の「神」ではなくて
心の鏡に写った、遍満する生命と絶対的な理解に満ちた「来るが如き」存在、に目覚めていない、それが、あなたです

苦集道滅
苦 生きている限り苦しみから逃れられない
集 苦しみには原因がある
道 苦しみの原因を取り除く実践の道を進まなければならない
滅 道によって、苦しみが消滅する
これは、仏教の基本的真理ではありますが、法界から見れば、苦集道滅は存在しません
実は仏教では、「努力して仏になる」には三大阿僧祇劫(さんだいあそうぎこう)という時間がかかるとされています
だんだん学習を重ね、試行錯誤し、経験を積み、賢くなって、輪廻転生を続け、失敗してまた振り出しに戻ったりしながら、成長し、寄り道したり、心地良い場所にしけこんだり、ドツボにはまり込んだり、フラフラと、あるいは、まっしぐらに進んでいって、調子に乗って全てチャラになって最初からやり直したり、だんだんと、三大阿僧祇劫かかって仏になります
三大阿僧祇劫は仏教の時間の単位で、
一劫が4億3200万年(梵天の一日)
阿僧祇が10の56乗
で、4億3200万年×10の56乗×3に大がついてますから、もっと長い時間です
ここまで長けりゃ、どうでもいいですけど
1296000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000年
ハハ、のんびり行きましょう
仏教は輪廻転生があるとしていますが、輪廻によって、学習効果があって賢くなるとしても、仏になるには三大阿僧祇劫かかるのです
まあ、とにかく、不可能でないにしろ、「努力して仏になる」のを諦めさせるために出来た話としか思えませんね
だから
仏教は努力主義じゃありません
しかし、何もしないでいい、ということでもないわけで、お釈迦様は、弦を緩めすぎても、きつく締めすぎてもいい音の出ない琴にたとえています
適度の緊張、ちょうどいい加減、がいいとされています
苦しみがなければ、誰も苦労しないのですが、生老病死はさし迫っています
三大阿僧祇劫かかって、全ての苦しみから解放されるはずが、それを、完全に速やかに、圓で頓に解決するわけです
極めて、虫のいい、要領のいい、棚ぼたの、努力のいらない、方法です
あっけなさ過ぎて、嘘のようです
まあ、手間のかかった表現ですが、圓頓以外に方法は無い、と言いたいわけです
止観、三密加持、など、仏教の歴史のなかで様々な方法が編み出されてきましたが、その基本になる考え方が圓頓です
歴史的に言うと、yogaとか三昧とかの言葉が古く
それが、仏教独自の言葉として、奢摩他samatha(止)・毘鉢舎那vipasyana(観)、三密加持と変遷していきます
今風に言えば、瞑想して、仏になるのです
努力して、仏になるのではありません
天台では、法華経の全部あるいは一部、阿弥陀経、般若心経などの大乗経典を読誦すると、坐禅止観、つまり瞑想しなくても間に合う、としています
それと、これに念仏が加わります
つまり、法界と繋がり一つになります
この辺は、慈覚大師などによって整理されたのですが、日本の伝統仏教が踏襲しています
観音経(法華経の普門品)、般若心経、阿弥陀経などの読誦で三大阿僧祇劫をワープします
三密加持は、かなり手っ取り早く霊験がありますから、どうしても現世利益に目が行きがちですね
難しいところです
念仏は、霊験をすっ飛ばして、来世に重点を置くのですが、これも極端な話ですよ
仏教は長い歴史がありますから、いろんな方法があって、迷うくらいです
ですが、基本は、圓頓です

無苦無集。故無世間。
むくむしゅう こむせけん
無道無滅。故無出世間。
むどうむめつ こむしゅっせけん
純一實相。實相外。更無別法。
じゅんいちじっそう じっそうげ きょうむべっぽう
苦も無く集も無し ゆえに世間無く
道も無く滅もなし ゆえに出世間無し
純に一実相にして 実相のほか さらに別の法無し
苦集道滅が無い境地になると、世間(俗世間)も出世間(仏教の修行)も無い
純粋に一つの実相があるだけで、実相のほか、さらに別の法は無い
鏡が法界と繋がり一つになることによって、実相だけになります
前の節と対になって順逆に圓頓を説明しています
圓頓章は短い文章ですが、よく見ると、いくつかの節に分かれています
非常に考え抜かれた、名文ですね
(順)
陰入皆如。無苦可捨。
無明塵勞。即是菩提。無集可斷。
邊邪皆中正。無道可修。
生死即涅槃。無滅可證。
(逆)
無苦無集。故無世間。
無道無滅。故無出世間。
純一實相。實相外。更無別法。
陰入皆如 無明塵勞。即是菩提 --->無苦無集--->無世間
邊邪皆中正 生死即涅槃--->無道無滅--->無出世間
それが、純粋に一つの実相だと
仏界--->己界--->衆生界 でもあります
自分が法界と繋がって一つになれば、ただそれだけで、衆生界にも善い影響があります
実相(法界)--->鏡=実相
実相が鏡に写ると、鏡は実相となる
鏡=実相--->世界=実相(法界)
鏡が実相になると、世界が実相になる
実相とは、鏡に写る前の世界のことです
感覚器官で感じる前のナマの世界
感じる前の世界ですから、苦も無ければ、我もありません
それが鏡に写っているんですが、写している鏡も鏡の中の世界です
目の前のPCのモニターが目に見える前の姿を想像してもらったらいいです
空も、太陽も、風も、隣の人も、神も、霊も、自分も、感覚器官で感じる前の姿があります
それが実相です
実相は法界と同じ意味です
実相という言葉は、他であまり使わないのです、それで、僕は法界と言っています
なにか、感情を含んだ表現がしたくて実相という言葉を使ったのかもしれません
冷たい連鎖反応のような世界でなく、血の通った、温もりの感触を表す言葉を捜したのでしょう
法界は、燦々と生きてるんですよ
で、これですね
密教の手順と同じです
密教の三密加持は、入我我入(にゅうががにゅう)と言って
実際は「本尊われに入り、われ本尊に入る」と二つの部分に分かれています
加持と言うと、仏の側からの働きかけ(加)を受け止める(持)というニュアンスになりますが、実感としては、自分も仏に入っていく、ということです
自分も入っていく、というのは、密教では身に印を結び、口に真言を唱え、意識を仏に集中します
あるいは、大乗経典を読誦します
また同時に、戒律を保つ努力をします(守れなければ反省します)
ぼんやり、ボケーっとしているのではありません
で、自分なりに仏に歩み寄って行くのを、自力とか聖道門とか言って、選ばれた人しかできないとか、凡人には無理、と言ったりして批判する時代もありましたが、実態は、三大阿僧祇劫をワープして、いとも簡単に仏になるスーパー近道なんです
やっぱり、こう
仏界---> <---己界
お互いが歩み寄って行くのであって
勝手気まま、やりたい放題、自由放任、てなことにはなりません
なにか、非常に常識的な落ち着き方だと思いますよ
慈悲に満ちた存在が手を差し伸べていて、こちらからも手を伸ばし、手を繋ぐ、と
心が通います

さて、長々と書いてきましたが、終わりに近づいてきました
皆さんが考えている仏教のイメージと、どうでしょう、近かったですか
僕は、高野山大学で真言密教を学び(たいしたことはないですけど)本山で行者の監督を1年間しました
奥之院の行法師をしたこともあります
それから、今いる寺の都合で、比叡山で一からやり直し、もう20年以上経ちます
真言と天台の両方知っていますが、ちゃんと勉強したのは真言ですので、真言密教の考え方のほうが詳しいのです
ですから、僕の考え方は、かなり真言的な天台、でしょうね
まあ、それでも、両方やった御陰で僕なりに仏教の流れが理解できました
インドのヴェーダやウパニシャッドの基礎の上に仏教が成立し、1000年程の間に、次第に純粋なお釈迦様の教説にインド古来の考え方が混合して密教になります
約800年間に渡り密教は隆盛を極めますが、12世紀頃、(日本の鎌倉時代頃)にイスラムに徹底的に破壊されインド仏教は滅びます
しかし、世界各地に伝播していた仏教は、発展を続けます
スリランカ、ミャンマー、タイなど南方では、比較的、お釈迦様の時代の様子が残されています
元々ヴェーダやウパニシャッドがありませんから、ほぼ原型が保たれています
チベットは国策でインド密教がそのまま輸入されましたが、ご承知のように中国共産党に弾圧されています
後期密教の性的要素が強くなりますが、仏教の伝統を失わない流れも引き継がれます
南方やチベットはインドから近いため、本場の影響を強く受けています
中国は、インドから地理的に遠いため、インド仏教が前後バラバラに伝えられました
ですから、順序を組み立て直す必要に迫られました
現在でも大きな異論がなく受け入れられている、経典の整理整頓をしたのが天台大師です
模倣でなく、独自の宗教的センスで仏教を再構成しています
中国に密教がもたらされたのが、今から1200年前位で、インド密教の最盛期です
ですが、中国社会に充分同化できませんでした
道教からの攻撃や、何回かの廃仏で弱体化していきます
伝教大師と弘法大師が中国に渡ったのは、ちょうど、インドから密教がもたらされた直後です
大まかな年表です
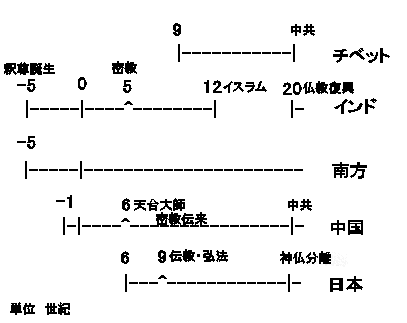
それで、中国で整理された仏教に密教を付け加える作業をしたのが日本です
弘法大師は密教中心で割り切ってしまいます
その為、弘法大師以後の発展はほとんどありません
伝教大師は密教の消化に苦労し、弟子が何人も中国に行き研究を重ねます
天台宗は真言宗の約3倍の経典を中国から持ち帰っています
八家秘録(平安時代入唐した八人の僧の請来目録)によると
真言宗関係の請来書
465部 888巻
天台宗関係の請来書
1201部 2326巻
天台宗は密教だけでも約3倍の経典を持ち帰っています
こういった努力が、その後の鎌倉仏教の基礎になります
圓頓章は天台大師が講述したものですが、結果的に、インド、中国、日本の仏教を繋ぐ基軸になりました
バラバラの経典を整理する時の基本になる考え方を知ることができ、同時に、多岐にわたる仏教の本質を示しています
短い文章でまとまっていますから、案外、仏教は単純で簡単なんじゃないでしょうか

法性寂然名止。寂而常照名觀。
ほっしょうじゃくねんみょうし じゃくにじょうしょうみょうかん
雖言初後。無二無別。
すいごんしょご むにむべつ
是名圓頓止觀。
ぜみょうえんどんしかん
法性寂然たるを止と名づけ 寂にして常に照らすを觀と名づく
初後を言うことなかれ 二無く別無し
これを圓頓止觀と名づける
法界が鏡から切り離されて静寂に包まれるのを止と名づけ、静寂でありながら、常に燦々と光明を放って輝くのを観と名づける
どちらが先ということではなく、二つ別々のことでもない
これを、完全で速やかな止観と名づける
この部分は、止観の話です
繋縁法界。一念法界。
縁を法界に繋ぎ 念を法界にひとしくする
の部分の「繋縁法界」が止で、「一念法界」が観です
繋ぐ、というのはyogaで、仏教より前からある瞑想を説明した言葉です
それを止という言葉で置き換えるのですが、これは、対象に心を「止めて」集中するからこのように言います
瞑想の分類から言えば、イメージトレーニングのような、気持ちの制御は、瞑想のほんの一部分にしかすぎません
これについては、広大な研究がありますが、長くなるので縮めます
身・口・意に分類します
身体的動作、行動などを通じた瞑想
ダンス、舞踏、掃除、演劇、ハタヨガ、経行(きんひん)など
口を通じた瞑想
念仏、読経、歌、朗読、詠唱など
意による瞑想
これが、普通一般に言われる瞑想ですが、読書、執筆なども含まれます
思いつくままに書きましたが、要は、
「法界と心がつながり一つになる」ということ全てです
「繋縁法界」=「法性寂然」=止
それが、ただ繋がるんじゃなくて「止」ですから、集中して散乱しません
「一念法界」=「寂而常照」=観
でもって、ボンヤリとボケーっとしてるんじゃなくて、光り輝くんです
集中して、輝く
つまり、これが、止観です
職人さんが、お客さんに喜んで貰おうと、精魂こめて仕事する
競技会で、皆の声援をうけて、期待に応えようと競技する
誰かの役に立とうと、自分のことを顧みず仕事に精をだす
などなど
一心不乱で輝いてますよねー
ですから、こういうことも、止観と考えます
それで、「法界と心がつながり一つに」なれば圓頓です
法界は、鏡のない、「感じる前の世界」のことですが
鏡とは、つまるところ我執です
で、
私利私欲の無い気持ちで、一心不乱になにかをしてる状態
それが、圓頓止観です
伝教大師はこれを
「己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」
と言っています
インドに始まった止観を、日本で、ほの暗いお堂の中の坐禅だけでなく、社会全般に通じる活動に作り替えたんです
その精神が、法然、親鸞、道元、栄西、日蓮などの鎌倉仏教の開祖を生み出しました

圓頓章の解説をまとめると
-------
完全で素早い方法
初めに「法界の心」につながれば、心の鏡に写し出された世界は真実そのものとなる
「法界の心」につながり、ひとつになれば、すべては真実となる
ちっぽけな、目に見える物、ちょっとした香りも、中道である
己界、佛界、衆生界、合わせれば法界全ての存在を説明できます
法界の側から見れば、全ての鏡の中の現実は、如であり、空です
ですから、苦として捨てるべきものが、どこにもありません
法界には苦しむべき我がありませんから、その原因もない、という境地
片寄ったこと、邪悪なことも、みな、中庸で正しいことであるので、仏教の修行として歩むべき道は無い
法界から見れば、鏡の世界の生死は涅槃と同じことで、苦しみを終焉させるため達成することなど、どこにも無い、という境地
苦集道滅が無い境地になると、世間(俗世間)も出世間(仏教の修行)も無い
純粋に一つの実相があるだけで、実相のほか、さらに別の法は無い
法界が鏡から切り離されて静寂に包まれるのを止と名づけ、静寂でありながら、常に燦々と光明を放って輝くのを観と名づける
どちらが先ということではなく、二つ別々のことでもない
これを、完全で速やかな止観と名づける
-------
お経の意味がわからないので書き下して欲しい、現代の日本語に翻訳して欲しい、と頼む人がいます
よく言うんですが、
「翻訳したほうがもっとわかりにくい」です
何回いったりきたり読み直しても、わかったような、わからないような
含蓄があって、いつも新たな発見があります
ここで解説していることは、まだまだ、意味の入り口でしかありません
「読誦どくじゅ」と言って、経本を手に持って、文字を見ながら(読)声を出して読んでいると(誦)、ふっと、いままでわからなかった部分の意味がわかる時があります
しばらく、また読誦し続けていると、わかったつもりの所が、もっと深い意味だったことに気付いたりします
その繰り返しです
それで、お経は、暗記してもいいですが、「読誦しなければならない」とされています
経典の読誦は、ですから、瞑想ですね
五種法師(ごしゅほっし)と言って
受持、読誦、解説、書写、如説修行
受持 じゅじ
経典を受け、持つ
まあ、どこかで経本を買い求めたり、貰ったりするのです
そして大事にします
読誦 どくじゅ
文字を見ながら、声を出して読みます
解説 げせつ
意味を調べたり、考えたりします
書写 しょしゃ
写経したり、印刷して他の人に教えてあげたりします
如説修行
お経に書いてある通り修行します
このどれもに、限りない功徳があります
それで、今ここでは解説をしてるのですが、これは、僕自身が一番ありがたいわけですね
仏教はもう2500年やってますから、やはり、計り知れない程の神仏の加護があります
でもそれは、「繋がって一つに」ならなければ実感できません
仏教は、単なる考えかたの羅列でなくて、生活態度や文化そのものなのです

當知身土 一念三千
故成道時 稱此本理
一身一念 遍於法界
とうちしんど いちねんさんぜん
こじょうどうじ しょうしほんり
いっしんいちねん へんのほうかい
まさに一念は三千の身土と知るべし
ゆえに成道の時これを本理と称し
一身一念は法界に遍ず
この部分は元の摩訶止観には無い部分ですが、現在は広く用いられています
一念三千の三千は、京都大原の三千院の名前の由来にもなりました
法界を
仏・菩薩・縁覚・声聞・天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄
の十界に分けて、それぞれの界にまた十界があります
合計百界に相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究境の十如があります
それが、五陰世間・衆生世間・国土世間の三世間にあります
10×10×10×3で三千です
三千世界とも言います
まあ、普通の人が、仏になったり、修羅になったり、餓鬼になったりすると
よくある話です
一念三千は摩訶止観の圓頓章の部分にはありません
ネットで検索すればいくらでも説明がありますので、十界、十如、三世間の説明は省略します
これは、仏教的な分類ですが、各宗教いろいろ言うわけです
クラス分けですね
理論は各種あるようですが、どうも、身分の違いがあるらしいですね
まあ、詳しく知らなくても間に合います
僕に言わせれば、こういう理論的部分にハマルと、延々と辻褄合わせを繰り返さなければならなくなります
アバウトでいいんじゃないでしょうか
仏教の場合は、「自分はいつか仏になるんだ」と思っていれば、それで、あなたは菩薩です
上から2番目です
僕的には、大変、都合のいい理論ですが、なんてったって、圓で頓ですからね
ただ、楽が出来るとは限らないのです
十界にそれぞれ十界がありますから、菩薩は、天界にも行きますが、餓鬼界にも、地獄界にも行くのです
それで
法界と繋がり一つになれば、一念が三千の世界に行き渡ります
「座を立たずして一切の仏事を成す」ということです
このあたりは、やはり本格的に修行しないと解らないでしょうねぇ

圓頓章は仏教の特徴を考えるうえで、わかり易くはないですが、要点がまとめられているのが、おわかりいただけたかと思います
残念なことに、仏教は、勉強するとなると、大変に複雑で難しいのです
天台の僧侶は、法要や儀式、日々の勤行の時には、ほとんどこの圓頓章を読みますから、一日に何回も読むこともあります
それで、自然と暗記し、少しづつでも、毎日理解が深まっていきます
ですから、特に勉強をしなくても、仏教的な考え方が身についていきます
頭で理解するのでは無く、自然と腑に落ちてきます
そのうえで、止観を実習すればかなりの効果があります
また、皆さんも、ちょこっとでも、坐禅や止観を実習なされば、圓頓に直に触れることができるでしょう
僕は、キリスト教やイスラムを信じる方も、圓頓止観を実習すれば、かなりの効果があると考えています
「光の瞑想」はある程度、そうした普遍性をもった方法として工夫したものです
http://chohoji.or.jp/shousei/saloon.htm
まあ、しかし、仏教では、仏様から慈悲の心がきて、自分も慈悲の心を持って、それが繋がって一つになって、自分が仏になる、のは許される考え方なんですが、一神教の信徒はせいぜい「神の愛に包まれる」で止まるでしょうね
文化的ブロックですね、僕に言わせれば
それでも、圓頓章は世界の文化に対する普遍性をもっていると思いますよ
なにせ、ホントのことが書いてありますから
唯一の神が何人もいるような世界は、不安定ですからいずれ終わります
神との契約に隷属し、閉鎖社会に生きるのか
自分の中に真実の根拠を見いだし、全てと繋がり一つになるのか
どうぞ、お選びください
![]()