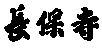笠原正夫
 菩提寺の選定
菩提寺の選定和歌山市から国道42号線を南下して約20キロ、海草郡下津町に長保寺がある。
11世紀には京都の権門と結びつき、浜中荘を形成して、この地域で権勢をほこっていた長保寺も、荘園体制が崩壊していく過程で中世的な権威は失墜していった。関ヶ原合戦後入国した浅野幸長は、名刹の衰亡を憂え、慶長6年(1601)に寺領5石を安堵したくらいであった。その後、子坊の最勝院住職恵尊法印が、元和年間に堂塔の修理をして、かろうじて長保寺の体面は保たれていた。
元和5年(1619)国がえによって、浅野氏は芸州広島へ転封し、かわって徳川頼宣が入国してきた。半世紀におよぶ頼宣の統治があって和歌山の近世体制は整っていくが、彼は南紀徳川家の菩提寺の選定もおこなった。「寛文六年南竜公(頼宣)この地を経歴し給ひて……旦その地山巒環抱して外幽にして内敝に万世兆域の地となすへきを察し給いひ、則ち仏殿一宇を建立し……」(『南紀徳川史』名著出版刊、第一巻)とあって、寛文6年(1666)に菩提寺は決定した。長保寺には、「吾可必以天台宗葬、葬儀有軽重、只於本寺可従其軽以営之、是無他」と、天台宗葬で質素な葬式を営むようにといった頼宣の遺言状が残されている。
これより16年前の慶安3年(1650)9月、頼宣の命をうけて、豪児僧正がひそかに菩提寺選定のため、和歌山付近の寺院を物色した形跡がある。「当寺(和歌浦雲蓋院)へ立寄られ候、逗留の内、長保寺、梅田釈迦堂、六十谷へ参られ候節の沙汰には、故大納言様(南竜侯)御廟の地かねてしらべ申され儀と潜に申候」(雲蓋院文書)とある。頼宣は、この時江戸にあって、豪児因州は、その候補として六十谷(和歌山市)の大同寺、梅田(下津町)の釈迦堂、浜中の長保寺などこの地方の名刹三ヵ寺をあげて江戸へ報告している。菩提寺の選定には、御三家の面目をかけて頼宣がかなりの配慮をしていたことがうかがえる。
寛文9年(1669)に、頼宣は原田権六ら3人の藩士を建立奉行に命じ、藩営事業として仏殿を建立した。これが現存している位牌殿である。寛文11年(1671)正月10日、南紀徳川の礎を築いた頼宣は大きな足跡を残して逝去した。彼の遺命によって同月24日に天台宗葬が営まれて山内に葬られた。
 藩侯の廟
藩侯の廟長保寺の霊域には歴代の藩侯の廟が並んでいる。このうち5代吉宗、13代慶福(家茂)が江戸の将軍家をついだために廟がない。御三家であり、55万石という大藩の藩侯の廟だけにいずれも豪華なものばかりである。この廟に使用された石材はどこから運んできたものか定かでなかったが、屋鷲組大庄屋記録(尾鷲市立図書館所蔵)の「御用留」の中に宝暦8年(1758)に、奥熊野尾鷲組梶賀浦と曾根浦の山から切り出されたことが記されている。6代藩主宗直の歿年が宝暦7年(1759)7月2日であるところから、宗直(大慧院)のものであろう。ついで明和2年(1765)5月にも曾根浦、梶賀浦からご用石が切り出されている。これは7代宗将(菩提心院)の廟の普譜に使った石材である。宗将は明和2年2月26日に江戸赤坂邸で逝去し、3月2日に江戸谷中感応寺で大葬し、11日に柩が江戸を発して長保寺へ向かっている(『南紀徳川史』第二巻)。
切り出されたご用石は、奥熊野から下津浦まで運ばれるのに紀伊半島を回って海路を運ばれていくため、沿岸の浦方へは、厳重な警戒を指示する触書きが送られている。この時に、大川浦(和歌山市)の専蔵船、林太夫船、彦三郎船と、梶賀浦の嘉右衛門船、五左衛門船などで運んだようである(『尾鷲市史』上巻)。8隻の回船でご用石2300個を運び、運賃は合計で銀4〆690匁を払っている。明治2年7月ごろ下津浦まで運ばれた石は、港から長保寺まで約2キロの道のりを運ばれた。長保寺の霊域で石工が加工して完成したものであろう。その他の藩侯の廟にも熊野石が多く使われている。
 長保寺領
長保寺領近世初期の長保寺は、本坊陽照院と地蔵院、福蔵院、最勝院、本行院、専光院の五子坊からなっていた。頼宣の死去ののち、寛文11年9月10日に、海士郡上村、中村(ともに下津町)と有田郡山田村(湯浅町)の3ヵ村であわせて500石が寺領として、2代藩主光貞から保障された(長保寺文書)。その翌12年(1672)9月10日の家老安藤帯刀直清在判の書状には、上村で290石3斗7升8合と中村で209石6斗2升2合の2ヵ村で500石と変わっている。それに浅野家から寄進された5石とで寺領505石である。かつて中世には荘園の所有者であった地位から、徳川家というスポンサーによって保障された知行主的な存在に変わっていた。長保寺は近世に入って完全に封建支配体制下に入ってしまった。
この505石は、本坊陽照院に200石、子坊の五ヵ坊はそれぞれ20石ずつを所領し、霊牌所墓地の年中諸用および役僧給料飯料などに100石、和歌浦雲蓋院の霊牌料が80石、御斉会料12石、鐘つき役料8石、釈迦堂仏供燈明料5石に内わけされている。
寺領の範囲は、その後幕末まで近世を通じて変わらなかったが、元治元年(1864)から明治元年(1868)の5カ年間における『収納高取調帳』をみると、石高は522石9斗余にふえている。寺領内において新田が開発されているからである。
505石ある長保寺領の総取分は、いちおう半分の225石2斗であったが(五公五民)、別表のように農民からの年貢の納入が滞ることがたびたびおこった。とりわけ享保時代における災害は連年的なものであり、長保寺領でも影響は殊のほか大きかった。寺領からは28〜45%ぐらいしか年貢が徴収できていないことからみてもそれがうらづけられる。長保寺の本坊子坊の六坊は、このような時に、和歌山藩の御蔵米の貸しつけを受けることによって切りぬけてきた。つまり足米である。しかし不足額全部を借りられたのではなかった。 長保寺陽照院第五世住職広然が記した「元文五申歳、御寺領下免御足米願之留」には、この年にいなごのため寺領で95石7斗余しか納米がなかった。